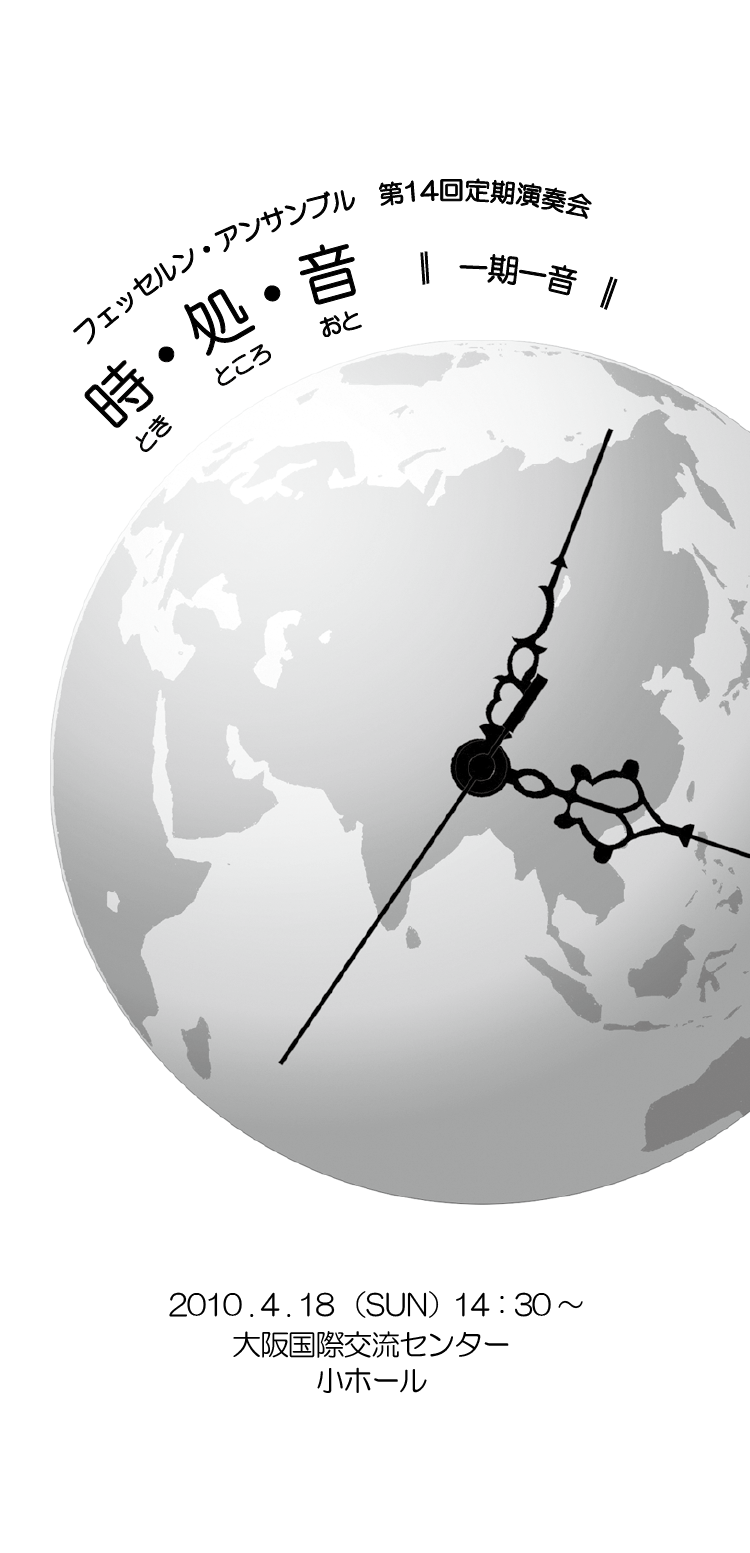
- Greeting -
「フェッセルン・アンサンブル 第14回定期演奏会」にご来場いただきましてありがとうございます。年一度こつこつとやってくるともう14回を数えることになりました。最初から来ていただいている方も、今回初めてこられた方も、春の休日の昼下がり、音楽の中に身をゆだねていただければと思います。
さて、今回はモーツアルト、クロイツァー、ドビュッシー、木下牧子と古今東西幅広く取り上げ、様々な「音」を楽しんでいただけるのではないかと思っております。本日の演奏会のタイトル「時・処・音」にはそんな意味を込めています。本日取り上げた曲達は、決して有名な曲ばかりではありません。加えて、邦人の現代音楽という聞き慣れないジャンルもあり、ついつい身構えてしまうのではないでしょうか?
少々私見ですが、私は音楽なんて理解できなくていいと思っています。そもそもわかる、わからないという軸で考えるのは評論家や学者だけでいいと思っています。目の前で繰り広げられる「音」の世界に身をゆだねてみる、ということだけで十分です。そこには厳粛な空間があったり、愉快な空間があったり、見たこと(聞いたこと)もないような世界が突然広がったり、そんな時間も空間も超えた体験ができるのが音楽だと思っています。
「一期一会」という言葉は茶道に由来します。「あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ないたった一度きりのものです。だから、この一瞬を大切に思い、今できる最高のおもてなしをしましょう。」という意味です。今回のもう一つのタイトルは、この一期一会を一文字変えて「一期一音」にしてみました。いうなれば 「あなたがこうして聞いている音は二度と巡ってこない たった一度きりのものです。」と。そして、私たち奏者は「今出来る最高の演奏」を目指しています。そして、それは今日ここに来ていただいた皆さんを、軽快と憂いが同居する空間(モーツアルト)や飾り付けたっぷりの空間(クロイツァー)、透明感と緊張感が交差するアンニュイな空間(ドビュッシー)や方向感覚を見失うような不思議な空間(木下牧子)といった世界にご招待いたします。非常に取っつきにくい曲もあるでしょう。しかし、そこに一度身をゆだねてみてください。特に現代音楽は未聴体験ができる、というのも楽しみの一面でもあります。理解する必要はありません。心の赴くままに音の世界に身をゆだねてみるのも、音楽の、そしてライブ(演奏会)の楽しみ方の一つだと思います。
本日はお忙しい中、ご来場くださいまして誠にありがとうございます。皆様と共に、時空を超えた一期一音を共有できればと願っています。
さて、今回はモーツアルト、クロイツァー、ドビュッシー、木下牧子と古今東西幅広く取り上げ、様々な「音」を楽しんでいただけるのではないかと思っております。本日の演奏会のタイトル「時・処・音」にはそんな意味を込めています。本日取り上げた曲達は、決して有名な曲ばかりではありません。加えて、邦人の現代音楽という聞き慣れないジャンルもあり、ついつい身構えてしまうのではないでしょうか?
少々私見ですが、私は音楽なんて理解できなくていいと思っています。そもそもわかる、わからないという軸で考えるのは評論家や学者だけでいいと思っています。目の前で繰り広げられる「音」の世界に身をゆだねてみる、ということだけで十分です。そこには厳粛な空間があったり、愉快な空間があったり、見たこと(聞いたこと)もないような世界が突然広がったり、そんな時間も空間も超えた体験ができるのが音楽だと思っています。
「一期一会」という言葉は茶道に由来します。「あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ないたった一度きりのものです。だから、この一瞬を大切に思い、今できる最高のおもてなしをしましょう。」という意味です。今回のもう一つのタイトルは、この一期一会を一文字変えて「一期一音」にしてみました。いうなれば 「あなたがこうして聞いている音は二度と巡ってこない たった一度きりのものです。」と。そして、私たち奏者は「今出来る最高の演奏」を目指しています。そして、それは今日ここに来ていただいた皆さんを、軽快と憂いが同居する空間(モーツアルト)や飾り付けたっぷりの空間(クロイツァー)、透明感と緊張感が交差するアンニュイな空間(ドビュッシー)や方向感覚を見失うような不思議な空間(木下牧子)といった世界にご招待いたします。非常に取っつきにくい曲もあるでしょう。しかし、そこに一度身をゆだねてみてください。特に現代音楽は未聴体験ができる、というのも楽しみの一面でもあります。理解する必要はありません。心の赴くままに音の世界に身をゆだねてみるのも、音楽の、そしてライブ(演奏会)の楽しみ方の一つだと思います。
本日はお忙しい中、ご来場くださいまして誠にありがとうございます。皆様と共に、時空を超えた一期一音を共有できればと願っています。
- Program -
W.A.モーツアルト
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ニ長調 第30番 K.306(300l)
Sonata fur Klavier und Violine D-dur K.306 (300l)
I .Allegro con spirito
II .Andantino cantabile
III .Allegretto
ヴァイオリン :宮木 義治
ピアノ :江本 直子
C.クロイツァー
Conradin Kreutzer (1797-1828)
ピアノ、クラリネットとファゴットのための三重奏曲 作品43
Trio fur Klavier, Klarinette und Fagott op.43
I .Maestoso – Romanze Allegro moderato
II .Andante grazioso
III .Rondo Allegro
クラリネット :橋本 頼幸
ファゴット :瀬尾 哲也
ピアノ :梅崎 衣理子
< 休憩 ~ Intermission ~>
C.A.ドビュッシー
Claude Achille Debussy (1862 – 1918)
プルミエ・ラプソディ(第1狂詩曲) クラリネットとピアノのための
Premiere Rhapsodie pour Clarinette et Piano
クラリネット :橋本 頼幸
ピアノ :梅崎 衣理子
木下 牧子
Makiko Kinoshita (1956 – )
ねじれていく風景 クラリネット、ヴァイオリン、ピアノのための
Twisting Landscapes for Clarinet in B , Violin and Piano
第1楽章
第2楽章
第3楽章
ヴァイオリン :宮木 義治
クラリネット :橋本 頼幸
ピアノ :江本 直子
- Program Notes -
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ ニ長調 第30番 K.306(300l)
モーツアルト
1778年に作曲されたマンハイム・ソナタという6曲のヴァイオリンソナタ集の最後を飾る曲である。マンハイムはドイツ西部の都市で、モーツアルトはこの年、職を求めてパリに旅立っている。このソナタ集の中ではホ短調ソナタ(K304)がおそらく一番有名と思われるが、このK306ソナタも6曲中唯一、3楽章構成でヴァイオリンとピアノが対等にスケールの大きな音楽を構成する聴き応えのあるソナタである。今日の演奏から少しでも西欧の華やかな雰囲気を感じていただけたら幸いである。
(Y.Miyaki)
ピアノ、クラリネットとファゴットのための三重奏曲 作品43
クロイツァー
昨年の演奏会に引き続き登場となったドイツの作曲家コンラディン・クロイツァーは、あまり名前は聞かないけれど、実は音楽愛好家では知る人ぞ知る作曲家、というわけではありません。少なくとも私は去年知りました。今回の三重奏曲も、演奏CDはほとんど出回っておらず、演奏を聴く機会は少ないので、貴重な演奏をお届けすることになります。
さて、現在はほぼ忘れられた作曲家の忘れられたこの曲ですが、なかなか面白い曲です。私が持った第一印象は「ドイツの作曲家の作品?」でした。華々しく始まる1楽章、牧歌的雰囲気の漂う2楽章、軽快な3楽章からなるこの曲は、重々しい部分がなく曲全体を通して明るく軽快な響き、トリルやターンといった装飾音がいたる所にちりばめられた派手さなど、どちらかといえばイタリアやフランスの曲ではと思うような雰囲気を持っています。演奏者の緊張具合はともかく、皆さんは肩肘張らず、気軽に寛いだ雰囲気で楽しく聴いていただければ幸いです。
(T.Seo)
プルミエ・ラプソディ(第1狂詩曲) クラリネットとピアノのための
ドビュッシー
フランスの作曲家ドビュッシーが1910年に完成させたパリ音楽院のクラリネットクラスの学年末試験のために作曲された曲です。今からちょうど100年前。この曲にこれ以上の解説は不要ではないかというぐらい、完成度の高い曲です。試験のために作曲されたという域を遙かに超えています。ピアノとのデュオでかかれているが後にピアノパートをオーケストラでアレンジされています。誰もが認める名曲で、現代に至るまで非常に多くの演奏会で取り上げらています。クラリネット奏者にとって大切なレパートリーです。同時に非常に難曲です。演奏時間もそれほど長くはなく、譜面上は基礎的な技術を求められているに過ぎません。しかし、印象派といわれたドビュッシーが表現しようとしたものを再現するのは、とんでもなく難しい一曲でもあります。
(Y.Hashimoto)
ねじれていく風景 クラリネット、ヴァイオリン、ピアノのための
木下牧子
木下牧子氏(1956~)はあまりメジャーな作曲家とは言えないが、合唱曲の邦人作曲家としては非常に人気が高く、中高生向けの平易な作品から高度なアンサンブル技術を要する難易度の高い作品まで多数発表している。そんな合唱の分野に重心を傾けていた彼女が近年、器楽作品にも力を注いでおり、今回演奏するこの曲も2004年に発表されたばかり(出版年は2007年)とまだ世に出されて年月が浅く演奏回数もさほど多くはない。
音域広く運動性に優れたヴァイオリンとクラリネットが紡ぎ出す音の連鎖の中にピアノが楔を打ち込む第1楽章、3つの楽器を雄弁に絡み合わせた奥行き深い第2楽章、技巧的でハイ・テンションな第3楽章とそれぞれ見事な対比を「ねじれていく風景」というタイトルで表現している。
本日彼女の作品に初めて触れるという方や現代音楽初体験の方には、私たちが試行錯誤して作り上げた木下牧子の世界観を存分に味わって頂ければと思う。
(N.Emoto)
- Members -
梅崎 衣理子(Eriko UMESAKI); ピアノ
 今回の演奏会がフェッセルン・アンサンブルデビューとなる梅崎さんは、これまでのピアノな人への我々のイメージを覆した期待の新星です。きちんと初練習から準備万端で望んでいたのは驚きを持って迎えられると同時に頭が下がりました(その驚きはおかしいというつっこみはその辺においときます)。今回ドビュッシーではクラリネットと、クロイツァーではクラリネットとファゴットという管楽器との2曲を担当する彼女は、元クラリネット奏者という経験を持ってます。楽器の種類が違えば微妙に異なる間合いも、管楽器奏者の微妙な間が経験としてわかっていることから、共演者としては大助かり。デビューからややこしい曲×2ですが、堅実にアンサンブルを支えつつ華々しいデビューを飾っていただけることでしょう。
今回の演奏会がフェッセルン・アンサンブルデビューとなる梅崎さんは、これまでのピアノな人への我々のイメージを覆した期待の新星です。きちんと初練習から準備万端で望んでいたのは驚きを持って迎えられると同時に頭が下がりました(その驚きはおかしいというつっこみはその辺においときます)。今回ドビュッシーではクラリネットと、クロイツァーではクラリネットとファゴットという管楽器との2曲を担当する彼女は、元クラリネット奏者という経験を持ってます。楽器の種類が違えば微妙に異なる間合いも、管楽器奏者の微妙な間が経験としてわかっていることから、共演者としては大助かり。デビューからややこしい曲×2ですが、堅実にアンサンブルを支えつつ華々しいデビューを飾っていただけることでしょう。
江本 直子(Naoko EMOTO); ピアノ
 早いもので江本さんとは今回で4回目の共演になります。いつもそのとっても細身の身体からは想像も出来ない鋭いタッチで音楽をリードしてくれています。でも最近はいろいろと忙しいようで、すこしお疲れ気味のご様子。でも、本番ではいつものように完全燃焼ですばらしいピアノを聴かせてくれることでしょう。打ち上げでは、カロリーの高~くておいしいものをいっぱい食べましょうね!
早いもので江本さんとは今回で4回目の共演になります。いつもそのとっても細身の身体からは想像も出来ない鋭いタッチで音楽をリードしてくれています。でも最近はいろいろと忙しいようで、すこしお疲れ気味のご様子。でも、本番ではいつものように完全燃焼ですばらしいピアノを聴かせてくれることでしょう。打ち上げでは、カロリーの高~くておいしいものをいっぱい食べましょうね!
瀬尾 哲也(Tetsuya Seo); ファゴット
 『ムーミンのパパ』のような瀬尾さん。一見、物静かで口数少なげな印象を受けるのですが、以外にお喋り好きだと判明!!楽器のお話からお仕事、マンションの理事会・・・とあらゆる会話が繰り広げられ、そこそこ、いや・・・果てしなくお喋りされます(笑)。そして、ファッションの一部のようにもなっているファゴット。その特有の持ち方の姿勢で背骨がずれまくり体の不調を訴えておられます!さてさて、練習中の瀬尾さんはというと、ファゴットの音色のごとく穏やかに、且つどっしりと構えて、一人もがき苦しみ突っ走る室内楽ビギナーの私を、いつも的確なアドバイスで導き、落ち着かせて下さいます。音からもにじみ出る瀬尾さんの包容力には本当に救われます。ムーミンパパ、今日も頼りにしています!
『ムーミンのパパ』のような瀬尾さん。一見、物静かで口数少なげな印象を受けるのですが、以外にお喋り好きだと判明!!楽器のお話からお仕事、マンションの理事会・・・とあらゆる会話が繰り広げられ、そこそこ、いや・・・果てしなくお喋りされます(笑)。そして、ファッションの一部のようにもなっているファゴット。その特有の持ち方の姿勢で背骨がずれまくり体の不調を訴えておられます!さてさて、練習中の瀬尾さんはというと、ファゴットの音色のごとく穏やかに、且つどっしりと構えて、一人もがき苦しみ突っ走る室内楽ビギナーの私を、いつも的確なアドバイスで導き、落ち着かせて下さいます。音からもにじみ出る瀬尾さんの包容力には本当に救われます。ムーミンパパ、今日も頼りにしています!
橋本 頼幸(Yoritaka HASHIMOTO); クラリネット
 感情の赴くまま演奏する私に頭脳派な橋本さんは、演奏中いつも冷静に崩壊の危機から救ってくれるとても心強いクラリネット奏者です。そしてメンバーの投げかけるどんな無理難題にもキャパシティーの広さと豊富な人脈を持って不可能を可能にする頼もしい人物でもあります。
そんな橋本さんは私の苦手な“メトロノームでカチカチ練習”をやたら推奨してきます。でもそんな地道な努力の積み重ねが今日のこの舞台を作り上げているのかと思うと、横着で超いい加減な私もカチカチが随分病み付きになってきました。
感情の赴くまま演奏する私に頭脳派な橋本さんは、演奏中いつも冷静に崩壊の危機から救ってくれるとても心強いクラリネット奏者です。そしてメンバーの投げかけるどんな無理難題にもキャパシティーの広さと豊富な人脈を持って不可能を可能にする頼もしい人物でもあります。
そんな橋本さんは私の苦手な“メトロノームでカチカチ練習”をやたら推奨してきます。でもそんな地道な努力の積み重ねが今日のこの舞台を作り上げているのかと思うと、横着で超いい加減な私もカチカチが随分病み付きになってきました。これからもこんな私たち「ピアノな人」を見捨てず根気強くお付き合い下さいね
宮木 義治(Yoshiharu MIYAKI); ヴァイオリン
 もうすっかりバイオリンソナタを自在にこなすようになってしまった(と思う)彼だが、意外にもソナタ歴は浅い。まぁ、浅いといっても2002年がソナタデビューなんだが。その時の因縁(?)のモーツアルトにまたもや挑戦する。前回のモーツアルトと違って今回のモーツアルトはひと癖もふた癖もある。今回はテクニックに加えて表現力まで問われることになってしまった。まるでフィギュアスケートのようだ。さらに、今回の宮木は好戦的だった。もう一曲の木下牧子の現代曲も拒否すると思った私の予想を覆して乗ってきてしまった。おかげで私は苦労した・・・。モーツアルトと現代曲。バイオリンの腕にさらに磨きをかけてまた新しい一面を見せてくれることでしょう。演奏が始まる前から楽しみにしているのは私だけではないはずだ。バイオリンの魅力と彼自身の魅力を存分に発揮してくれることだろう(と信じている←プレッシャー(笑))
もうすっかりバイオリンソナタを自在にこなすようになってしまった(と思う)彼だが、意外にもソナタ歴は浅い。まぁ、浅いといっても2002年がソナタデビューなんだが。その時の因縁(?)のモーツアルトにまたもや挑戦する。前回のモーツアルトと違って今回のモーツアルトはひと癖もふた癖もある。今回はテクニックに加えて表現力まで問われることになってしまった。まるでフィギュアスケートのようだ。さらに、今回の宮木は好戦的だった。もう一曲の木下牧子の現代曲も拒否すると思った私の予想を覆して乗ってきてしまった。おかげで私は苦労した・・・。モーツアルトと現代曲。バイオリンの腕にさらに磨きをかけてまた新しい一面を見せてくれることでしょう。演奏が始まる前から楽しみにしているのは私だけではないはずだ。バイオリンの魅力と彼自身の魅力を存分に発揮してくれることだろう(と信じている←プレッシャー(笑))
文化や言葉が違っても
音符は世界共通である。時代が変わっても同じである。ドの音はドの音でしかない。だれがなんと言おうがドの音である。ただ、それはだれがどのようにドの音を奏でるかで大きく変わるのも音楽である。絵画や彫刻は保存状態が良ければ、いつだれが見ても同じものを見ることができる。しかし、音楽は奏者が変われば違う響きになるし、聞く場所が変わっても異なる。たとえ同じ奏者であっても、全く同じ演奏は不可能だ。
一期一音。
一生の内でこの瞬間、ここでしか聞けない音を
聞くことができた、と思っていただければ、
今回の無謀なプログラムも救われるかも知れません
一生の内でこの瞬間、ここでしか聞けない音を
聞くことができた、と思っていただければ、
今回の無謀なプログラムも救われるかも知れません
