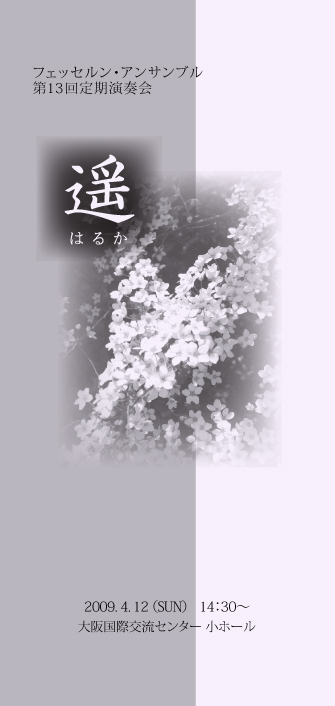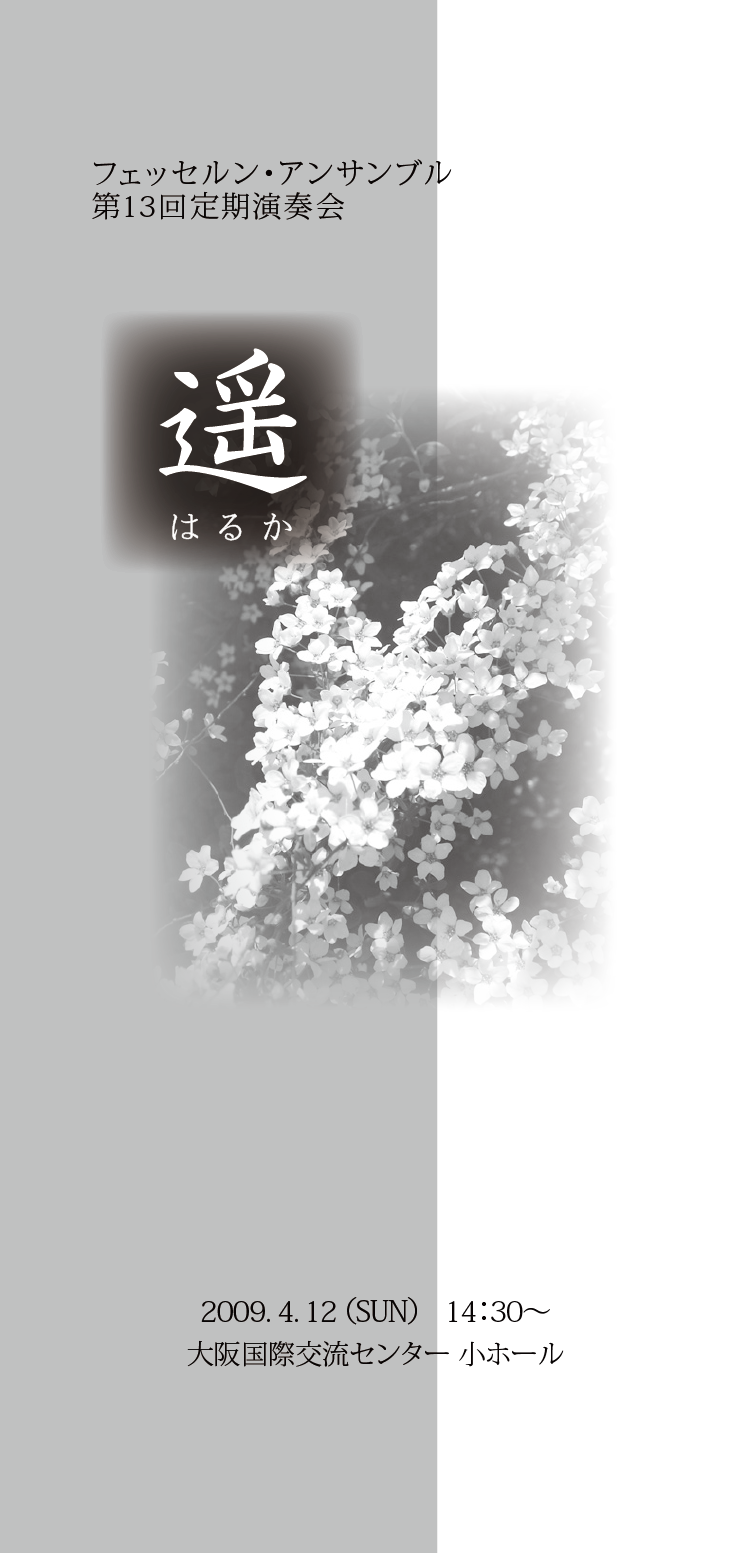
- Greeting -
「フェッセルン・アンサンブル第13回定期演奏会」にご来場いただきましてありがとうございます。13年間、年に一度の演奏会を続けてきました。メンバーにも公私ともにいろいろな変化がありました。それでも続けていけるというのは音楽のすばらしさではないかと思います。
第13回の演奏会のテーマに「遥」を選びました。そして本日演奏する曲は全て三重奏(トリオ)で構成されています。ヴァイオリン・チェロとピアノのいわゆる標準型から、クラリネット・チェロとピアノ、ソプラノ・クラリネットとピアノそしてオーボエ・ファゴットとピアノという変則型まで様々な組み合わせで、様々な響きが広がります。また、本日演奏します曲もベートーベン(古典)からカリヴォダ・クロイツァーも含みブラームスに代表されるドイツロマン派、プーランク(フランス現代)まで三重奏(トリオ)に込めた作曲家の思いをお楽しみ頂けると思います。
さて昨年は「つながり」というテーマで人と人とのつながり、音楽の現代までのつながり、死を意識した作曲家の見た風景というつながり、などをテーマにしました。そして今年は「遥」がテーマです。「遥」か昔に作曲家が見たもの、思い描いたものを、今私たちが受け止めることができます。そして私たちが受けたものを次の「遥」か先につなげていく役目があります。遥か昔から遥か先の未来に・・・。連綿と綴られてきた想いは、その時々の奏者が演奏することでつなげていくことができます。人間が音を発見した太古の昔から、バッハやベートーベンが理論立ててつなげてきたドイツ音楽の系譜、ドイツ音楽からフランス音楽への派生、古典から現代への変化、これらは全て連続した流れの中に存在します。そこには、とぎれることなく遥か昔から遥か未来へつながる「音楽の流れ」があります。
その流れの中に私たちは身を置いております。私たちは音楽を演奏しています。そして、その音楽を聴くことができます。音楽は何があっても無くなることはありません。心の中に刻まれたものは決して消えることなく、その流れの中で遥か彼方につないでいくことができます。音楽は言葉や理屈を超えて全てのものを平等にしてくれます。そこには音以外に何もいりません。今年のテーマである「遥」には、過去から未来に向けて綴られていく音楽は私達と本日来られた皆さんが担っています、という想いをこめています。
最後になりましたが、本日はお忙しい中、ご来場くださいまして誠にありがとうございます。「遥」に込められた想いを皆様と共有できれば私たちにとってこれほど幸せなことはありません。
第13回の演奏会のテーマに「遥」を選びました。そして本日演奏する曲は全て三重奏(トリオ)で構成されています。ヴァイオリン・チェロとピアノのいわゆる標準型から、クラリネット・チェロとピアノ、ソプラノ・クラリネットとピアノそしてオーボエ・ファゴットとピアノという変則型まで様々な組み合わせで、様々な響きが広がります。また、本日演奏します曲もベートーベン(古典)からカリヴォダ・クロイツァーも含みブラームスに代表されるドイツロマン派、プーランク(フランス現代)まで三重奏(トリオ)に込めた作曲家の思いをお楽しみ頂けると思います。
さて昨年は「つながり」というテーマで人と人とのつながり、音楽の現代までのつながり、死を意識した作曲家の見た風景というつながり、などをテーマにしました。そして今年は「遥」がテーマです。「遥」か昔に作曲家が見たもの、思い描いたものを、今私たちが受け止めることができます。そして私たちが受けたものを次の「遥」か先につなげていく役目があります。遥か昔から遥か先の未来に・・・。連綿と綴られてきた想いは、その時々の奏者が演奏することでつなげていくことができます。人間が音を発見した太古の昔から、バッハやベートーベンが理論立ててつなげてきたドイツ音楽の系譜、ドイツ音楽からフランス音楽への派生、古典から現代への変化、これらは全て連続した流れの中に存在します。そこには、とぎれることなく遥か昔から遥か未来へつながる「音楽の流れ」があります。
その流れの中に私たちは身を置いております。私たちは音楽を演奏しています。そして、その音楽を聴くことができます。音楽は何があっても無くなることはありません。心の中に刻まれたものは決して消えることなく、その流れの中で遥か彼方につないでいくことができます。音楽は言葉や理屈を超えて全てのものを平等にしてくれます。そこには音以外に何もいりません。今年のテーマである「遥」には、過去から未来に向けて綴られていく音楽は私達と本日来られた皆さんが担っています、という想いをこめています。
最後になりましたが、本日はお忙しい中、ご来場くださいまして誠にありがとうございます。「遥」に込められた想いを皆様と共有できれば私たちにとってこれほど幸せなことはありません。
- Program -
J.W.カリヴォダ
Johann Wenzel Kalliwoda (1801-1866)
故郷の歌 作品117(ソプラノ、クラリネットとピアノのための)
Heimathlied fur Sopran, Klarinette und Klavier op.117
ソプラノ :川村 操代
クラリネット :橋本 頼幸
ピアノ :井上 恵里子
C.クロイツァー
Conradin Kreutzer (1797-1828)
水車(ソプラノ、クラリネットとピアノのための)
Das Muhlrad fur Sopran, Klarinette und Klavier
ソプラノ :川村 操代
クラリネット :橋本 頼幸
ピアノ :井上 恵里子
L.v.ベートーベン
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
クラリネット、チェロとピアノのための三重奏曲 変ロ長調 作品11「街の歌」
Trio fur Klarinette, Violoncello und Klavier “Gassenhauer-Trio” B-dur op.11
I .Allegro con brio
II .Adagio
III .Allegretto. Tema- 9 variations -Coda
クラリネット :橋本 頼幸
チェロ :梅本 直美
ピアノ :井上 恵里子
< 休憩 ~ Intermission ~>
F.プーランク
Francis Poulenc (1899-1963)
ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲
Trio pour piano, hautbois et basson
I .Presto
II .Andante
III .Rondo
オーボエ :崎里 直己
ファゴット :瀬尾 哲也
ピアノ :江本 直子
J.ブラームス
Johannes Brahms (1833-1897)
ヴァイオリン、チェロとピアノのための三重奏曲 ロ長調 作品8
Trio fur Violine, Violoncello und Klavier H-dur op.8
I .Allegro con brio
II .Scherzo (Allegro molto)
III .Adagio
IV .Allegro
ヴァイオリン :宮木 義治
チェロ :梅本 直美
ピアノ :江本 直子
- Program Notes -
故郷の歌 作品117 (ソプラノとクラリネットとピアノのための)
カリヴォダ
カリヴォダはきわめて多作な作曲家であり、たとえばローベルト・シューマンのような同時代の音楽家から、高い評価を受けていた。作品数は数百曲にのぼり、そのうちおよそ250曲に作品番号が付けられている。作品番号117と付けられたこの曲は、クラリネットと声との不即不離の関係を保って、独特な味わいを感じられる曲である。
(M.Kawamura)
水車 (ソプラノとクラリネットとピアノのための)
クロイツァー
ドイツのビーダーマイヤー期を代表するオペラ作曲家、指揮者。この曲では、クラリネットの温かみのある音色で「ドイツ・リート」の世界を詩情豊かに表現されており、歌との兼ね合いがおもしろい。
(M.Kawamura)
クラリネット、チェロとピアノのための三重奏曲 変ロ長調 作品11「街の歌」
ベートーベン
ピアノ三重奏曲といえば、バイオリン・チェロ・ピアノの組み合わせが一般的です。この曲はバイオリンの代わりにクラリネットが使われていますが、バイオリンで演奏することも多いようです。しかし、管楽器的な要素も強いと感じる曲でもあります。ベートーベンとしては特にこだわってなかったようですが。作品番号11番という非常に初期の頃の作品でシンプルかつスタンダードにまとまっています。裏返していうとごまかせない、純粋に奏者の力量とアンサンブルの完成度が問われる曲とも言えます。一般に「街の歌」と呼ばれていますが、これは3楽章の旋律がウィーンの流行歌だったオペラアリアを主題にしているからだそうです。たしかに全楽章通して親しみやすい曲です。気分はすっかりウィーンで、優雅な気持ちになれる一品です。(Y.Hashimoto)
ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲
プーランク
プーランクは「フランス6人組」と呼ばれる、詩人ジャン・コクトーの周辺に集まった作曲家の集まりのひとりで、主に20世紀前半に活躍しました。管楽器を用いた室内楽曲を数多く残していて、そのどれもが軽妙洒脱で親しみやすいメロディーにあふれています。しかしよく聴いてみると、メロディーはバロックや古典派のような重厚な和音に支えられ、また音楽の振る舞いもかなり厳格なものになっていることが分かります。このように、一見正反対とも思える要素が混在していることから、「ガキ大将と聖職者が同居している」と評されたこともあったようです。さて、「のだめカンタービレ」でも取り上げられたこの曲は、1926年に完成した作品です。1921年頃からクラリネット、チェロ、ピアノという編成で構想していたようですがしっくり来ず、発想を変えて、フランス・バロック的なオーボエ、ファゴットとしたところ、作曲はスムーズに運んだといいます。急-緩-急の3楽章構成で、当時一緒に勉強していたラヴェルの助言も取り入れながら、第1楽章はハイドンのアレグロ楽章を、第3楽章はサン=サーンスのスケルツォ楽章をそれぞれ念頭において作曲したとプーランクは述べています。また第2楽章は優美なモーツァルト風です。全体としては、大戦間の束の間の休息とでも言うべき世間の雰囲気を反映してか、深刻さのない、何とも楽しい軽快な音楽となっています。なおこの曲はスペインの作曲家ファリャに捧げられました。(N.Sakisato)
ヴァイオリン、チェロとピアノのための三重奏曲 ロ長調 作品8
ブラームス
その作品番号から考えるとごく若い時代の作品と思ってしまいがちであるが、実は現在出版されている楽譜や発売されているCD、演奏会で取り上げられるそのほとんどが、晩年のブラームス自身が大きく手を加えた改訂版なのである。残念ながら初版を演奏したり聴いたりしたことが無いのでその違いは分からないが、いろいろな資料によると「青年らしく本能のまま思いつく美しい旋律を綴った曲が、驚くべき確実さをもって論理的に再構成された」とのことのようである。初版および改訂版が正式に残っている唯一の曲でブラームスを研究する上で貴重な足がかりとなる曲でもある。調性上も最初の楽章が長調で始まり終楽章が短調で終わる、あまり例のない構成であり興味深い。しかしこのような背景を知らずとも、その美しい旋律は聴き手の奥深くにすっと入ってくるに違いないだろう。(でも、この曲、とっても難しいんです・・・)(Y.Miyaki)
- Members -
井上 恵里子(Eriko INOUE ; ピアノ
 彼女を一言で表すと「天然」です。それもかなりの「ど天然」・・・(失礼)必ず??な行動や答えが返ってきます。ここで数々の天然伝説をご紹介出来ないのは残念ですが、ピアニストとしての彼女は、感受性豊かで、非常に歌心のある人です。私は彼女の清らかな心に随分と助けられました。それは今から彼女が奏でる「真のある柔らかな音」を聴いて頂ければご理解頂けるでしょう。また、何事にも興味を持ちチャレンジし、それがどんなに大変な事であろうとも、逃げずに楽しもうとする彼女の志に私は憧れ続けているのです。
彼女を一言で表すと「天然」です。それもかなりの「ど天然」・・・(失礼)必ず??な行動や答えが返ってきます。ここで数々の天然伝説をご紹介出来ないのは残念ですが、ピアニストとしての彼女は、感受性豊かで、非常に歌心のある人です。私は彼女の清らかな心に随分と助けられました。それは今から彼女が奏でる「真のある柔らかな音」を聴いて頂ければご理解頂けるでしょう。また、何事にも興味を持ちチャレンジし、それがどんなに大変な事であろうとも、逃げずに楽しもうとする彼女の志に私は憧れ続けているのです。
梅本 直美(Naomi UMEMOTO); チェロ
 今回でトリオは3回目、初めてご一緒させて頂いたのもブラームスでした。当時は梅本さんの冷静かつ鋭いツッコミにちょっぴりたじたじ…。私の中で梅本さんは「クールなお姉さま」なのでした。そして今回2回目のブラームス。難曲なだけに未だかつてないほどの練習時間の中、梅本さんの意外なキャラを発見!実はおとぼけな一面も持ち合わせたのほほん系♪そしてあの音大生特有の不思議な感じ。自分と同じ匂いに今ではすっかり親しみ感じてます。そんな梅本さんの演奏で最も尊敬するのは、アンサンブルの中で常に他楽器との連携をうまく取りながら、旋律を受け持てば一瞬にして曲に深みを与える包容力。今日のブラームスではしょっぱなからやってくれます!
今回でトリオは3回目、初めてご一緒させて頂いたのもブラームスでした。当時は梅本さんの冷静かつ鋭いツッコミにちょっぴりたじたじ…。私の中で梅本さんは「クールなお姉さま」なのでした。そして今回2回目のブラームス。難曲なだけに未だかつてないほどの練習時間の中、梅本さんの意外なキャラを発見!実はおとぼけな一面も持ち合わせたのほほん系♪そしてあの音大生特有の不思議な感じ。自分と同じ匂いに今ではすっかり親しみ感じてます。そんな梅本さんの演奏で最も尊敬するのは、アンサンブルの中で常に他楽器との連携をうまく取りながら、旋律を受け持てば一瞬にして曲に深みを与える包容力。今日のブラームスではしょっぱなからやってくれます!
江本 直子(Naoko EMOTO); ピアノ
 この定期演奏会に5年連続出演を続けている彼女はすごい!日頃は仕事でとても忙しくしているので、本番大丈夫かな?という周囲の心配を退けての当日の魅せっぷりは誰にも真似出来ません。今日の演奏も楽しみにです!彼女と2人で、「ソロのピアノもいいけれど、アンサンブルがしたい!」と学生の頃に中庭で叫んでいたのが懐かしい今日この頃。実現している奇跡がこれからも続きますように。
この定期演奏会に5年連続出演を続けている彼女はすごい!日頃は仕事でとても忙しくしているので、本番大丈夫かな?という周囲の心配を退けての当日の魅せっぷりは誰にも真似出来ません。今日の演奏も楽しみにです!彼女と2人で、「ソロのピアノもいいけれど、アンサンブルがしたい!」と学生の頃に中庭で叫んでいたのが懐かしい今日この頃。実現している奇跡がこれからも続きますように。
崎里 直己(Naoki Sakisato); オーボエ
 崎里氏と知り合ってまだ数年だが、彼をとりまく環境はいろんなとこでどんどん変わっていっている。仕事、結婚、住居とまさに人生の節目というか激動の時期のはずだが、彼のオーボエはいたって安定していてうらやましい限り。そんな彼だからプーランクチームの要として、アバウトなFg吹きと“ぴあのな人”を牽引できているわけです。○歳若い彼に引っぱってもらいながら2年連続でともにプーランクと格闘している私としては、申し訳ないやらで頭が上がりません…。
崎里氏と知り合ってまだ数年だが、彼をとりまく環境はいろんなとこでどんどん変わっていっている。仕事、結婚、住居とまさに人生の節目というか激動の時期のはずだが、彼のオーボエはいたって安定していてうらやましい限り。そんな彼だからプーランクチームの要として、アバウトなFg吹きと“ぴあのな人”を牽引できているわけです。○歳若い彼に引っぱってもらいながら2年連続でともにプーランクと格闘している私としては、申し訳ないやらで頭が上がりません…。
瀬尾 哲也(Tetsuya Seo); ファゴット
 楽器の種別と奏者の性格との間には関連性があるとよく言われます。ファゴットといえばそのとぼけたようでホンワカした音色と、木管の低音を支える縁の下の力持ちといった少し控えめな役割が特徴です。瀬尾さんはその音色どおりのとても穏やかな人です。そしていつも地道に譜面をさらってこられ、合わせの練習でうまくいかないことがあっても、言い訳じみたことは決して言われません。これは、私のような自己顕示の体現のような楽器(さて何でしょう?)の奏者にとってはとても尊敬すべきところであり、見習わなくてはと思っています。そんな瀬尾さんも昨年に引き続き2回目の出演。今回もユーモラスなソロを交えながら、堅実な演奏を聴かせてくれるでしょう。
楽器の種別と奏者の性格との間には関連性があるとよく言われます。ファゴットといえばそのとぼけたようでホンワカした音色と、木管の低音を支える縁の下の力持ちといった少し控えめな役割が特徴です。瀬尾さんはその音色どおりのとても穏やかな人です。そしていつも地道に譜面をさらってこられ、合わせの練習でうまくいかないことがあっても、言い訳じみたことは決して言われません。これは、私のような自己顕示の体現のような楽器(さて何でしょう?)の奏者にとってはとても尊敬すべきところであり、見習わなくてはと思っています。そんな瀬尾さんも昨年に引き続き2回目の出演。今回もユーモラスなソロを交えながら、堅実な演奏を聴かせてくれるでしょう。
橋本 頼幸(Yoritaka HASHIMOTO); クラリネット
 最近ようやくその風貌と実年齢が一致してきた橋本氏(通称パパ、本当に二児の父)は、本業?の設計事務所運営に加え、あちこちの大学で教鞭をとっており、常人の理解を超える超多忙な毎日を送っている。四月からは大阪以外にも生活の拠点を持つらしく、人一倍睡眠時間が必要な私にはとてもまねが出来ない。そんな忙しい中でも練習には必ずつきあってくれ、演奏会の事務作業も、いやな顔一つせず核となって行ってくれている。フェッセルンがここまで長く続いてきたのは、間違いなく彼によるところが大きい。パパ、健康にはくれぐれも注意して、これからもヨ・ロ・シ・ク!
最近ようやくその風貌と実年齢が一致してきた橋本氏(通称パパ、本当に二児の父)は、本業?の設計事務所運営に加え、あちこちの大学で教鞭をとっており、常人の理解を超える超多忙な毎日を送っている。四月からは大阪以外にも生活の拠点を持つらしく、人一倍睡眠時間が必要な私にはとてもまねが出来ない。そんな忙しい中でも練習には必ずつきあってくれ、演奏会の事務作業も、いやな顔一つせず核となって行ってくれている。フェッセルンがここまで長く続いてきたのは、間違いなく彼によるところが大きい。パパ、健康にはくれぐれも注意して、これからもヨ・ロ・シ・ク!
宮木 義治(Yoshiharu MIYAKI); ヴァイオリン
 ズバリ!! 宮木君とは、フェッセルンに必要不可欠な人。そして裏社会?のボス。橋本君からメンバーに連絡があると阿吽の呼吸で宮木君が素早く返事をかえす。いつも返事が遅~い我々に対して、口ではああしろこうしろと言わないけれど、自らの態度でみんなに軽く一喝を入れてくれます(注1 本人はそんなつもりはないでしょうが・・・)。練習も富山から遙々来るだけでも大変なのに、文句どころか、本番に向けコツコツと練習し「次はブラームスの分厚い音作りをしておきます」と一言。『練習しとけよ』と言われてるように感じるのは私だけではないはず(注2 本人にはそんなつもりはないでしょうが・・・)。決して辛口なタイプではなくご覧のとおり、温かみのあるボスです。
ズバリ!! 宮木君とは、フェッセルンに必要不可欠な人。そして裏社会?のボス。橋本君からメンバーに連絡があると阿吽の呼吸で宮木君が素早く返事をかえす。いつも返事が遅~い我々に対して、口ではああしろこうしろと言わないけれど、自らの態度でみんなに軽く一喝を入れてくれます(注1 本人はそんなつもりはないでしょうが・・・)。練習も富山から遙々来るだけでも大変なのに、文句どころか、本番に向けコツコツと練習し「次はブラームスの分厚い音作りをしておきます」と一言。『練習しとけよ』と言われてるように感じるのは私だけではないはず(注2 本人にはそんなつもりはないでしょうが・・・)。決して辛口なタイプではなくご覧のとおり、温かみのあるボスです。
川村 操代(Misayo KAWAMURA); ソプラノ
 さかのぼること約2年。初めて彼女に会った時に非常に荒削りではあるが(ゴメン!)、何とも魅力的な声を出す人だと思った。大阪出身、沖縄在住。既婚一児の母。井上さんの高校からの同級生。う~ん。しばらく理解するのに時間を要してしまったがすっかり慣れてしまった。その経歴と歌声にいちいち驚かなくなった。彼女が練習に来るのも別に普通のことと思ってしまうし、私と井上さんとで昨年秋に沖縄で演奏会をやったのもごくごく日常の延長上に思えてしまう。今年はカリヴォダとクロイツァーに挑戦。あまり知られていないが非常に美しい曲達です。きっと魅力的に歌い上げてくれるでしょう。
さかのぼること約2年。初めて彼女に会った時に非常に荒削りではあるが(ゴメン!)、何とも魅力的な声を出す人だと思った。大阪出身、沖縄在住。既婚一児の母。井上さんの高校からの同級生。う~ん。しばらく理解するのに時間を要してしまったがすっかり慣れてしまった。その経歴と歌声にいちいち驚かなくなった。彼女が練習に来るのも別に普通のことと思ってしまうし、私と井上さんとで昨年秋に沖縄で演奏会をやったのもごくごく日常の延長上に思えてしまう。今年はカリヴォダとクロイツァーに挑戦。あまり知られていないが非常に美しい曲達です。きっと魅力的に歌い上げてくれるでしょう。
音楽は永遠に残っていきます
誰かの心に残った音楽は、音楽を遥か彼方から、遥か彼方へ、紡いでいくことができます。音楽は確実に誰かの心の中に残すことができます。
そう思うと、なんだかがんばろうって思えます。